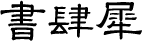テーマを超えた表現の深淵にふれて
小学校にあがる前のわずかな期間、父のすすめで絵画教室に通ったことがあった。それから六十三歳になってしまった現在まで、絵画とは不思議な関わりを持ち続けてきたように思う。
絵を描くことがことさらに好きでも上手でもなく、ましてや高校時代には美術部に籍を置きながら、ロック・バンドに夢中になっていた変なじぶんを振り返ってみても、絵と濃密に向かい合った場面などただの一つも思い浮かばない。それなのになぜか、美術の世界からは離れまいというぼんやりした意志だけはずっとあり続けたように思う。
そんな私の、表現への淡い憧憬を壊し、表現することの意味を自覚させてくれることになったのは、一九七五年、東京国立近代美術館で開催された「香月泰男遺作展」であった。
記憶が曖昧で、なぜそのとき観に行ったのかは覚えていない。もしかして香月泰男とシベリア抑留という共通体験のある文芸批評家・内村剛介の評論や詩人・石原吉郎の作品に彼のことが書いてあったのかも知れない。ただはっきり覚えているのは、目の前にある独特のトーンを持った香月泰男の作品が、それまでに体験したことのない興奮を呼び起こしてくれたということだけだ。
色彩の存在感と価値を、「〈私の〉地球」や「月の出」などで知り、リズムの意味を「帰国」「煙」や「奉天(左)(右)」などに感じた。そして何よりも圧倒的な「涅槃」や「雪」には、生きること自体の質量を教えられたような気がしてならなかった。何ものかに煽られるように、次の日ふたたび会場に足を運んだことを思い出す。二十五歳の夏だ。
当時の私にとって、それはもはや絵画ではなく、香月泰男という作家を磁場として収斂されてくる人間いっさいの時空の表れというような印象で、その時空に屹立している香月泰男の孤独で重厚な倫理そのもののようだった。キャンバスにぶ厚く定着されたマチエールの粒子が、妙にリアルな存在感を持ち、彼の倫理がその粒子に埋め込まれているようにも思えるほどだった。
《シベリヤ・シリーズ》というテーマをさえ作品は超えていたように思う。美術でも音楽でも、ましてや文学でもなく、その全てのような存在。たまたま絵画という様式をとったに過ぎない表現、表現とはつまるところこういうものを言うのだ、そんな感触を、知識としてではなく身体の感覚として味わうことのできた稀な体験だったように思う。