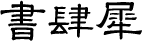「節電」という言葉が、あたかも戒律のような響きをもって、私たち一人ひとりの暮らしの中に押し寄せてきている。まるで「欲しがりません、勝つまでは」の精神に近づいてきているようにも感じる。もちろん「無駄電」を推奨したい訳ではさらさらない。
ちょうど1973年に起こった第一次オイルショック(世界同時不況)の時もそうだった。詩人石垣りん(1920年〜2004年)は、そんな今と酷似した社会情勢を背景に、詩やエッセイを書いていた。
当時ひとり暮らしをしていた彼女は、勤めから誰もいない狭い部屋に帰って、まず天井から吊るした照明器具の小さな明かりを点す。ほんのりと明るい白熱電球だ。彼女はこの癒される明かりを出来ることなら一日中点しておきたい衝動にかられる。つまり読みかえると、いつも、せめて明かりのともった部屋に帰ってきたいと思っていたのだろう。ほんとうにちっぽけな贅沢としてそれくらい許されるだろう、と。
厳密な表現はもう忘れてしまったが、そのニュアンスだけは鮮明に覚えている。たしか詩作品ではなく『ユーモアの鎖国』に収録されたエッセイだったと記憶しているが、もう手許にはなく確認できない。けっして主張的な表現ではないのに、こころの奥深いところにいつの間にか入っている。国の電力政策、電力会社の都合といった実利的な条件のみで、為政者は杓子定規で私たち一人ひとりの暮らしに「節電」という戒律を押し付けてくる。詩人石垣りんはそんな無機的な力に対して、ソフトに、そして深く、実にさりげなくラジカルな闘いを挑んでいたのだと思う。
現在、石垣りんが表現したようなデリカシーは、もしかしたらセンチメンタリズムとしか感受されないかも知れないことをおそれる。それだけ私たちの抒情の深度が上げ底化され、変容してしまっていると考えられるからである。