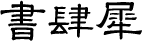わが国の歴史を研究している専門的な学者や研究者は、その研究の対象としている時代や年代ごとに数多く存在している。そして研究発表も学会の機関誌(紙)や大学の紀要、また専門書の出版をとおして毎年数えきれないほど公にされている。しかし、その多くは狭いアカデミズムの中で細々と読まれ、一部のディープなムラ社会の中で流通しているというのが現状に近い。せっかくの研究成果もなかなか一般社会の読者にまでは到達できていない状況にある。学問・研究とはそもそもそういう孤独な領域なのだと言われてしまえばそれまでだが…。つまり、筆者が言いたいのは、地道な努力で積み上げられてきた貴重な研究成果が、残念ながらなかなか社会化されるルートや場面を持てないでいるということである。ではいったい何故そういうことになるのか。いつもその疑問に立ち返ってしまう。
筆者の考えでは、研究論文の文体、様式が、そればかりではなくもしかしたら研究者自身のプライドや特権意識もその問題に大きく関与しているように見受けられる。とにかく文章が硬く、情感がはぎ取られて孤高感が漂っている。俗っぽく言い換えてしまえば研究者の書く文章そのものがとっつきにくいのだ。研究者はなぜ小説のような文体でじぶんの研究を表現できないのか。いや、しようとしないのか。なにも研究者にフィクションまがいの創作をしてほしいと言いたいのではない。また情に溺れてほしいと言いたいわけでもまったくない。研究内容をもっと日常感覚に根ざした、日常のことばで表現してほしいということに尽きるのだ。血が通った文章を書いてほしい、ただそれだけのことなのである。情感を削ぎ落としたクールなことばこそが理性・知性に貫かれた研究論文のことばであるかのように、長いアカデミズムの伝統の中で、いつしか勘違いされてしまっているように思えて仕方がないのである。