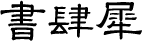子どもの頃、外灯のあかりに照らされる雪のシルエットを眺めるのが好きだった。夜中にトイレに起き、そっとカーテンをめくり、その様子を眺めるのである。音のない白色の雪片の舞いは、ほどよく乱れ、煌めき、幻想的かつ抒情的な世界であった。翌朝、1メートルほどの積雪があっても、何の苦もなかった。雪掃きは親の仕事であり、子どもにとってはもっぱら、雪だるまつくり、雪合戦、サンダルのようにつっかけて滑るスキーのためのワンダーランドにほかならなかったからである。
還暦をとっくに越えたいま、雪はその抒情的な仮面をすっかり脱ぎ捨て、暮らしに重くのしかかる恐怖然としたものに変ってしまっている。心身の老いは風景の受容をも否応なく変えてしまうものらしい。降りしきる雪を苦痛として感受してしまうじぶんを哀しいと思いつつ、積雪をイメージして迎える朝ほど厳しいものはない。
もう一度、舞い降りる雪に幻想的な抒情性を感じとれる自分の心を、なんとかしてとり戻せないものなのだろうか。心身の老いに抗い、対峙しうるもう一人の相対化された自分を創出する必要性を、ひしひしと感じている今日この頃なのである。