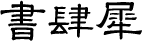二宮尊徳の名を知らない人は稀だが、彼がどんな人物だったかを知っている人も少ない。少年の頃学校の庭でみた奇妙な彼の像を想い出して、いまそこにコッケイさを感じない人はさらに少ない。あいまいにぼくらの前に存在していて、あいまいに忘れ去られようとしているのが二宮尊徳である。
学校の庭に据えられた程の人物。校庭に、ある意図のもとに据え置いた蔭の人物とその時代。これらは現在すっかり無化されてしまったようである。つまり時代は或る時期を境に彼を理念としても象徴としても葬ったということになる。
わが国の精神史の特質が尊徳の像の処遇ひとつのなかにもまばゆく反映している。いつもこうだったし、さまざまな安寧や錯乱を人々に強いてきたのも、そんなやり方だった。
いまわたしは個人の生涯の時間と歴史の時間との関連について、あるいはドラマについて、しみじみと重さを感じている。確実に断絶しつつどこかで繋がっていることをぼんやりと感じている。
二宮尊徳がどんな人物だったか急に気になって調べたことがあった。学生の頃だ。卒論のテーマにしようとしたこともあったが、彼がまとわされてしまったいろんな虚偽や偏見を払い除けるだけでもそうとうの作業になることは必至であった。まじめな学生でなかったわたしはそれに耐えられなかったのである。ちょうど江戸後期の禅僧・大愚が現在「人間良寛」なんていうかたちでしっかり神格化されているのと同じやり方で、二宮尊徳もおあつらえむきのシンボルにまつりあげられ、本体を深く隠されてしまっていた訳である。アウレリウスもニーチェも、もしかしたら、宮沢賢治も中原中也もそうだったのかも知れない。さようなら神話たち。
わたしは二宮尊徳像と二宮尊徳があまりにも無縁であることを識ったとき、ひとつの態度を教えられた。一個の人間によって担われた思想的営為はあくまでも全円的に構築されたものである限り、その全過程を検証しない限り肯定も否定も本質的には不毛であるということだ。シンボライズされたものというのはヤバイ虚偽でしかないことが多いことを識らされた。
戦後の風潮の中にあって安藤昌益がもてはやされ二宮尊徳が闇の中に放りこまれたこと自体はどうでもよいが、その理由については検証に値する。時代精神の推移がそうさせたとするなら、そんなものは一人の人間の思想的営為とは全く無関係である。一人の思想は時代の中で翻訳される以前に、それ自体として認識され理解されることを恋こがれているものだ。
時代精神の方は、その時々の為政者やマス・メディアが都合に合わせて、一個の人間によって培われた思索を担ぎ出し、アレンジし、コラージュし、別物に変質させながら流通させるものでしかないと言い切ってしまいたくなるほどだ。
「戦意高揚に資した」と戦後になって痛烈に批判されることになった保田与重郎も、「左翼的な思想を煽動した思想家」などと、お門違いな風説に包囲された吉本隆明もそうだったのかも知れないと思うと、思想者の孤独な呼吸音が聞こえてきそうになる。両者とも、そんな単相な思索者の範疇を軽々と越境していたのだから。