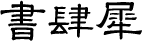戊辰戦争における新政府軍との戦いで一般論的に言えば負け知らずだった庄内藩も、秋田戦線を軸に戦況を最後まで有利に展開していたが、慶応4年(1868)9月26日、ついに奥羽越諸藩全体の動向とのかかわりの中でやむなく恭順降伏するに至る。しかしながら、庄内藩に対し新政府が行なった戦後処理は、会津藩に対する藩領の全面的な没収や斗南(現在の青森県むつ市)への転封という冷酷極まりない処遇とは異なり、東征大総督府参謀西郷隆盛の寛大な計らいによってさしたるお咎めもなく許されたとされている。私感では、この歴史記述はその流れにおいてどうもミステリアスと言わざるをえない。以前から、そこには隠された何かがあるような気がしてならなかった。理解するためには庄内藩が朝敵にされた経緯から考えてみる必要があるのだ。
ましてやここに庄内藩の菅実秀(すげさねひで)という人物を持ち出すとさらに謎が深まっていく。菅実秀という人物について、この時点(戊辰戦後)だけに絞って見てみると、新政府軍を代表して会談に臨んでいた黒田了介(清隆)との交渉のなかで、その庄内藩への処分をきめた人物が西郷隆盛であることを知る。西郷と菅の直接交渉があったわけではない。その黒田のことばを通して菅は西郷隆盛の思想に興味を持ち、江戸に西郷を訪ねるようになり、さらに旧庄内藩主酒井忠篤等とともに明治3年8月から翌年3月まで鹿児島を訪れ、西郷にいろいろ教えを請うた人物ということになっている。そしてその教えを、明治22年(1889)2月11日、大日本帝国憲法発布の特赦によって、西南戦争での西郷隆盛の賊名が除かれたのを機に、赤沢経言や三矢藤太郎に命じて「南洲翁遺訓」(西郷隆盛の考えや教えをまとめた書)を編纂させ、その出版物の配布をとうして西郷隆盛のいわゆる「敬天愛人」思想(註)を全国に知らしめた人物ということになる。その西郷隆盛と菅実秀をめぐる逸話そのものが、あたかも勝海舟と西郷隆盛の江戸城内における無血開城を決めた会談(この会談も実は駐日英国大使ハリー・パークスの指示によるもので、西郷はあくまでも江戸総攻撃を断念したくなかったという説が有力のようだ)のように、西郷隆盛のもう一つの美談として、今なお鹿児島と庄内の両地方で営々と語り継がれているわけである。
いっぽう庄内藩の戦後処理には次のような経過があったことを忘れてはならない。新政府はまず最後まで庄内藩への戦争協力を惜しまなかった豪商本間家に対する仕置きを断行している。時の大蔵卿大隈重信に呼び出され、本間家では庄内藩の降伏直後(月日は不明)、まずは5万両の献金を申し付けられ、これを納付している。つまり、新政府はまずもって金銭の問題から庄内藩の戦後処理に入って行ったことを重視してみて行く必要があるのだ。つづいて明治元年(1868)12月、新政府から庄内藩(酒井家)の会津若松への転封が命じられるが、なんとか家臣団と領民による反対運動が実りそれは免れた。資料がなく分からないが、反対運動が何事もなく新政府軍に認められるような状況とは考えにくく、この過程にも当然金銭のやりとりがあったと考えた方がむしろ自然のような気がする。そして翌明治2年(1869)6月、今度は磐城平への転封の沙汰が言い渡されたのである。しかしここでも庄内藩は70万両の献納を条件に転封を免れようと動いている。つまり新政府の目的が金銭であることを見抜いたうえでの時宜を得た提案であったようにも思えてくる。もちろん戊辰戦争の直後で、藩には金がなく領内で基金を募り、士分の者は財産を売り8万7千両、鶴岡の町民1万8千両、酒田町民9千7百両、本間家では先の5万両とは別にさらに5万両を都合し引き渡したとされている。そしてもちろん藩主であった酒井家でも先祖代々の宝物などを売ってようやく政府から要求された金額の半分、つまり35万両を明治政府に納め、最終的に転封を免れたというのである。ここで他藩の処分を例にあげてみると、仙台藩や米沢藩といった同盟の主軸をなした藩は減封と責任者の処刑(斬首もしくは切腹)。磐城平藩は新政府に7万両を献納しての所領安堵。相馬(中村)藩は1万両で所領安堵という具合。つまり庄内藩が納めた35万両(しかもこの額は表立ったもの)は際立った印象を受ける。
このように新政府(西郷隆盛)が庄内藩に対して比較的寛大な態度で接したと言われている背景には、当時全国の豪商の中でもずば抜けた力を有していた本間家の財産(経済力)があったことは明らかで、見てきたように、公にされている額だけみても本間家が新政府に納めた金額はなんと都合10万両にも及んでいるのである。そして会津若松への転封が撤回された事情などを考慮すると、これがすべてであったとはとても考えにくい状況だったのである。まさしく「本間様には及びはせぬが、せめてなりたや殿様に……」と俗謡にまで歌われる本間家であった。
ところで菅実秀という人物には、西郷隆盛に関わるもうひとつの驚くべき過去があることは、これまであまり知られていない。その周辺については、山形新聞の記者であった高嶋米吉が、昭和53年に黒田傳四郎というペンネームで著した『やまがた幕末史話』(東北出版企画)に詳しく書かれている。その内容を知れば、いかなる事情があっても菅が西郷隆盛を崇拝するようになるなどということはあり得ない、そんな印象をもつことになる菅の知られざる一面が紹介されている。小生はむしろこちらの菅に、庄内藩が追いつめられて行く幕末期の歴史的な経過を考え合わせてみても、本来の素に近い人間菅実秀を感じてしまうのだ。敗戦後に菅が西郷に近づいたのは、薩摩・長州の世の中での藩主酒井家とその領民たちの将来を思えばのことだったのではあるまいか。藩の重臣である家老たるもの、そのように考えるのが筋だったにちがいない。だが、そのような人倫を思う以前に、そう推察したくなる2つの大きな理由があった。1つ目は、慶応3年(1867)12月まで時間を巻き戻して見る必要がある。遡れば「薩摩藩邸焼き討ち事件」の折、庄内藩への出役命令と同時に幕府から別の密命が下されていたという事実だ。その密命とは幕臣小栗忠順が公私にわたって信頼できると考えていた庄内藩江戸留守居役松平権十郎ならびに藩士菅実秀に対する西郷隆盛の暗殺命令であった。そして即座に「西郷隆盛暗殺挺身隊」を結成させていたという事実にほかならない。江戸市中で強盗、放火、強姦といったあらゆる狼藉を働いている500人もの浪士たちを操っている黒幕が西郷隆盛である証拠を幕府がつかんでいたからであった。メンバーは庄内藩内きっての腕利きと目されていた石井有恒、俣野建八、菅沢八重次、朝比奈泰吉、重田範正、神戸善十郎の6名。菅実秀はその実行部隊の指揮を任されていたのである。「薩摩藩邸焼き討ち事件」とは周知のように江戸市中の治安維持を任されていた庄内藩(支藩である松山藩も含む)を主力部隊として、鯖江藩、岩槻藩、上山藩に出役命令が下った事件である。つまり菅は、以前より幕臣小栗忠順(4藩に薩摩藩邸への出役を命じた人物)と日常的に親交があったばかりではなく、深いところで信用されていたということでもあったのである。そして理由の2つ目として、西南戦争に際し援軍を要請してきた西郷軍に対し、菅はもっともらしい理由を述べて派兵を断っていることである。けっきょく庄内から西南戦争での西郷軍に加わって戦った旧藩士は2名だけだったようである。とりわけひとつ目の理由として挙げた「西郷隆盛暗殺挺身隊」結成に関する事実は、「西郷翁遺訓」にまつわる美談とはどう考えても馴染まないのだ。菅も小栗忠順を慕っており、日常的な交流のなかで小栗は菅の嫁を紹介するほどの間柄であったという。しかもその小栗が慶応4年(1868)4月、新政府軍によって隠遁先で罪なく斬首された事実を菅がどう受け止めていたのか知る由もないが、そこからストレートに西郷隆盛礼讃へと至る精神的回路は誰が考えてもミステリアスなものと言わざるを得ないはずである。
そんな2つの庄内藩内の戊辰前後をめぐる話(本間家が用立てた大金と菅実秀の過去)を考えると、戦後処理に関する西郷隆盛と菅実秀の美談は、どうも怪しいと言わざるを得ないのだ。詳細はこれからの調査になるが、これまで読んだ資料から判断するともちろんその伝説的美談は表層的(菅が酒井家と領民のためにとった政治的な判断)にはあり得ても、どうもその内部にはおおきなねじれや断層が隠されているように思えて仕方が無いのである。
(註)……西郷隆盛の思想「敬天愛人」の意味を現代語で表現すると次のようになるようだ。「人それぞれには、天から与えられた「天命」というものがあり、それに従って、人は生きているのである。だからこそ、人はまず天を敬うことを目的とするべきである。天というものは、「仁愛」すなわち人々を平等に、かつやさしく愛してくれるものであるので、「天命」というものを自覚するのであれば、天が我々を愛してくれるように、人は自らも他の人に対して、天と同じように、「慈愛」を持って接することが何よりも必要である」(tsubu氏のHPより)