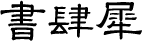NHK BSー2で放映している「岩合光昭の世界ネコ歩き」シリーズをみていて、ふと思った。あの画面全体に流れる穏やかな時間、そして愛しき猫たちが闊歩する何事も起こらない空間。これらってもしかしたら私たち人間の至福の日常性を表現している暗喩なんじゃないだろうか。味わい深いナレーションもふくめて大好きな番組のひとつである。 その独特の時間がながれる映像にオーバーラ …
続きを読む
犀のつぶやき
少ない上山藩軍の情報
賊軍(謂れのない蔑称!)として戊辰戦争を戦った上山藩軍の資料は、現在ほとんど残っていない。軍服はおろか、戦陣で綴られたであろう日記や報告書なども残存している話を聞いたことがない。敗色濃厚な流れを察知したとき、軍は敵に見られてはまずい資料を何よりも先に焼却処分してしまうからなのだろうか。 このたび「上山小銃大砲隊」の木村慎也氏より貴重な資料を提供していただいた …
続きを読む「明治日本の産業革命遺産」考
このたび、世界遺産への登録をめざした「明治日本の産業革命遺産」のリストが公表された。筆者もそのこと自体はすばらしいことだと思う。だが、それをみて驚いたのだ。その驚きとは「横須賀製鉄所(造船所)」が含まれていないことである。誰が考えても、いの一番に挙げられてしかるべき産業革命遺産だろうに…。そのいっぽう、なぜか「松下村塾」が選ばれているという不可解なリストと言 …
続きを読む歴史は人によってつくられる
《陸奥に 桜狩りして思うかな 花散らぬ間に 軍せばやと》 繊細な抒情を微塵も感じられないこの和歌の作者をご存知だろうか? 奥羽鎮撫総督府下参謀で長州藩士の世良修蔵である。奥羽鎮撫軍の一行が京都を出て奥羽に向かったのが旧暦の慶応4年3月6日(大坂港を出たのは11日)というから、現在の暦だと京都はちょうど桜の季節だったのかもしれない。そして3月18日、仙台寒風沢 …
続きを読む小栗忠順の先見性
ゴールデン・ウイークでとことん疲れ果ててしまっているはずのタイミング=5月9日(土)午前10時〜 「小栗忠順の先見性」というテーマで、上山城でお話しさせて頂きます。 私たちは教科書や副読本で、いやというほど勝海舟について、太平洋を渡った咸臨丸とセットで、あるいは江戸城の無血開城にまつわる西郷隆盛との会談などで教わってきましたが、小栗忠順については「誰?」とい …
続きを読む「黒船来襲」再見
謀略に謀略を重ねて念願の武力倒幕を果たした後、新政府は自らの「国造り物語」の制作に着手する。いわゆる勝てば官軍の歴史記述に他ならない。私たちの脳裡に未だ真実であるかのように擦り込まれている《浦賀に突如来襲した「黒船」の脅威》も、その一つの成果なのである。 嘉永6年(1853年)に、マシュー・ペリー率いるアメリカ合衆国海軍東インド艦隊の蒸気船2隻を含む艦船4隻 …
続きを読む上山の戊辰戦争関連史跡
1. 官軍墳墓 ……… 上山藩が奥羽鎮撫総督府の命令により、慶応4年4月23日、庄内藩征討戦に出陣。八聖山を拠として六十里越の警備の任についている。その作戦行動において、無念にも斥候(偵察)の任務に当たっていた菅谷友尉(19歳)、谷野廣平(17歳)2人の藩士を同日に失っている。その官軍兵士として没した2人の墳墓 =「官軍墳墓」が市内軽井沢の浄光寺境内に建って …
続きを読む戊辰巡りを再開・仙台編
4月5日(日)、本格的な春の到来を待たず、久しぶりに戊辰巡りを再開した。天気には恵まれなかったがのんびり気分、車で仙台まで出掛けて来た。 仙台藩校養賢堂の名残を唯一今に留める正門、そして英傑・玉蟲左太夫の墓碑。このふたつをこの目でしっかり見る事が今回の絞りにしぼったターゲットだった。 以前、養賢堂のあった場所(現在の宮城県庁のある勾当台)を訪れた事はあったが …
続きを読む「羽州上山城下温湯記」発見!
元禄15年に書かれた「羽州上山城下温湯記」なる文書が見つかった。 上山の温泉が、月秀上人によって発見されたことは、今は上山に住んでいれば小学生でさえ教わって知っている。それがまた当市の観光事業の根幹を掌っていることも万人が認めるところである。 しかしその裏付けの話となると決定的な史料は存在していないようなのだ。 じつに不思議な話である。 去る3月29日、我家 …
続きを読む「廃仏毀釈」
ほとんど知られていないが慶応3年(1867)12月9日の軍事クーデター「王政復古」(岩倉具視・西郷隆盛・大久保利通らの謀略)のあと、新政府によるもう一つの誤謬が進行し始める。「廃仏毀釈」である。日本古来のおおらかな信仰が否定され、国家神道への収斂をもくろむ強制的な歩みが開始されたのである。多くの寺や仏像が焼かれ、僧侶は否応なしに神官に、それを拒絶する僧侶は追 …
続きを読む