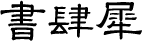「…この頃(註:御一新直後)、京都・嵯峨野などで林が荒れ始めた。嵯峨野の風景が変わり始めたのである。それは、剪定などを怠り美観維持の作業が行われなくなったことに因る。御一新前にこれを行っていたのは幕府である。太政官政府の大久保利通は、陳情を受けて初めてこのことを知った。幕府は、そこまでやっていたのかと驚いたのである。大久保が政治とは何ぞやということを理解した …
続きを読む
犀のつぶやき
歴史研究書と文体
歴史研究書を読んでいると辛い。言語表現がなんともストイック過ぎて、血の通っている人間が書いているとは思えないケースが多い。もっと自然に、私たちが日常語を発する時の呼吸やリズム、そして感性に近いところで書いて欲しいと思う。だからと言ってもちろん、湿気を含んだ過度な感情を滲ませてはいけない。 さらに、巻末につく「註」や「参考文献」のオンパレードには呆れかえってし …
続きを読む近況2題「大八忌と偲ぶ会」
6月18日は、毎年参加させて頂いている「大八忌」のため、天童市にある妙法寺・観月庵に足を運んだ。いつも楽しみにしている講話、今年は近年見つかった吉田大八の書状のこと。近藤守利氏が2年を要して翻刻した新発見の書状で、なかなか進まない藩政改革にいらだっている若き吉田大八の心情が綴られている。そればかりではない。明和4年(1767)、山県大弐事件に連座し、上州小幡 …
続きを読む至上の価値について
人間にとっていちばん大切な事って何か。いや、いちばん大切なものとして思想化すべきものは何か。この、青年期に考えるような命題を、あらためて還暦を過ぎた人間である自分に投げかけてみる。すると、これがけっこう難しい問題である事がわかる。 かつて吉本隆明が書いている。 《……生まれ、婚姻し、子を生み、育て、老いた無数のひとたちを畏れよう。あのひとたちの貧しい食卓。暗 …
続きを読む海外拡張主義の思想
史的に探っていくと、維新以降の日本海外拡張主義の端緒がみえてくる。多くの論考は昭和初期における日本軍国主義の台頭からの潮流として捉えてしまいがちだが、根っこは幕末期に熱病のように流行った過激な攘夷思想の内部に胚胎されていたもののようにみえる。日清戦争〜日露戦争〜日中戦争〜太平洋戦争を貫通している流れは、折々の世界情勢の変化に左右される形で戦争状態を進行させて …
続きを読むゲームソフトに、我思う。
自分はゲーマーではないのでやらないのだが、どうしてロードプレイングゲームに、暴力や武力に頼らず知力で難局を乗り越え、世界平和を成し遂げるような超難解な外交官ゲームがないのだろう? ふと、そう思った。 もし完成すれば、宗教問題、民族問題、イデオロギー問題、資源問題、エネルギー問題、経済摩擦問題といったあらゆる要件を盛り込んだ、究極の世界平和を実現させるまさしく …
続きを読む歴史の綾の不思議さ
2013年2月8日にも書いたが(下記サイト参照)、歴史の綾は実にデリケートなものである。 血脈は大義より深し ここで上に掲載した内容と関わる、歴史の綾の微妙さを物語る話を、血脈の視点からもう一つ書いておきたい。 それは、時の上山藩主松平信庸(のぶつね)の父信宝(のぶたか)の正室が戸沢右京亮正胤(うきょうのすけまさつぐ:正実の祖父)の娘秀姫であったこと …
続きを読む《エチュード》短詩:舌を巻く
《短詩》舌を巻く 糸のように孤独な 三日月の笑み なまめかしい植物の 半透明な葉脈 耳鳴りにちかい 音色のシンコペーション おだやかな曲線を裂く 歴史の兇暴 輪郭線をひた隠す 虹の気品 すべての前で 舌を巻く
続きを読む「やまがた好古酔連」近況
4人の若き古文書解読者から成る集団「やまがた好古酔連」の近況をお知らせしたい。 6月1日発行予定「やまがた街角《夏》」(八文字屋刊)に、メンバーのひとりである佐藤正三郎氏(上杉博物館学芸員)が、論考を寄せている。前号の田中大輔氏についで「やまがた好古酔連」第2回目の発表ということになる。 山形市内の旧家(乃し梅佐藤屋、後藤又兵衞旅館)に残されていた古文書から …
続きを読む抒情詩人・鈴木健太郎
明治42年5月25日、山形県南村山郡宮生村宮脇(現在の上山市宮脇)に父鈴木善三郎、母なかの長男として一人の詩人が生まれた。父は「実直に働く典型的な入婿」で、母は「『文芸倶楽部』から泉鏡花の小説だけを集め」、自分で一冊の本にして愛読していたほどの女性だったとある。なるほどと思う。彼が詩を書き始めることになったのは15歳前後から。19歳の時には「新山形」の新聞記 …
続きを読む